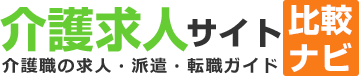福祉用具プランナーってどんな資格?資格の取得方法まで詳しく解説! 作成日:2018.04.04
最終更新日:2020.01.23
数ある福祉・介護系の資格の中で福祉用具プランナーという資格がよく分らないという方は多いと思います。
この記事は、「福祉用具プランナー」について、分かりやすく書いていきます!
福祉系の資格について、以下のようなイメージを持っている人は、なかなかたくさんいます。
- 福祉の資格を取得したい
- どの資格を取ればいいのか分からない
- 似た名前の資格が多くて迷う
- 資格は欲しいけど、スクールに通うのは面倒くさい
このような方におすすめなのは、「福祉用具プランナー研修」です。実は、福祉用具プランナーは、持っていると便利な資格なんです!
福祉用具プランナーとはそもそも何かということから、取得方法や名前のよく似た福祉用具専門相談員との違いまでしっかり説明するので、介護業界に興味をお持ちの方はぜひ最後まで読んで下さい!
福祉用具プランナーとはなに?簡単に解説
まずは福祉用具プランナーとは何かご紹介します。
そもそも、福祉用具プランナーとは「福祉用具を必要とする高齢者や障害者に対し、必要な福祉用具の選択と援助、適切な使用計画を査定、利用の支援及び提供状況をモニター・評価まで行うことのできる専門家」とテクノエイド協会に定義付けされています。
「ちょっと何のことかよく分からない…」という方も多くいらっしゃると思うので、以下で詳しく説明していきます。
福祉用具プランナーは福祉用具を選ぶ職業!
福祉用具プランナーは、端的に言うと「福祉用具を選ぶ専門家」です。
高齢者や障害者の方が福祉用具を使う際に、以下のようなことを指導します。
- 正しい使用方法や使用頻度
- 使用後の利用者のチェック
- 再評価
高齢者や被介護者の身体状況は日々変化するデリケートなものです。変化に適切に対応する福祉用具の選定が必要になります。
その選定の判断基準を明確にするために、「福祉用具プランナー」という専門家の存在が重要なんです。
福祉用具ってどんなもの?
福祉用具とは、以下のようなものを指します。
- 車いす
- 杖
- 介護用のベッド
- 補聴器
民間資格だけど社会的な役割を担える!
福祉用具プランナーの社会的役割とは、福祉用具を世に広める情報提供、福祉用具の使い方の相談窓口、指導者、苦情窓口、そして使用道具選定の支援者などを指します。
福祉用具プランナーは、テクノエイド協会が認定する民間資格です。
「民間資格ってことは、あんまり使えないの?」と思うかもしれません。実はそんなこともなく、社会的役割もしっかり担っています。
これらの役割を担うことができる資格が、福祉用具専門プランナーなのです。
平成9年から始まった新しい資格ですが今では1万4,653人が取得しています。
福祉用具プランナー取得方法
取得方法
まず福祉用具プランナー認定元であるテクノエイド協会の福祉用具プランナー研修を受講し、研修の全てのカリキュラムを修了し、協会が出題する修了試験に合格した後、修了証書書の交付完了の3ステップあります。
- テクノエイド協会の福祉用具プランナー研修のカリキュラムを修了
- 修了試験に合格
- 修了書交付完了
カリキュラムには受講条件があるので注意!
気をつける必要があるのは、カリキュラム受講条件と実務経験が必要なことです。
カリキュラム受講条件は以下です。
- 指定福祉用具貸与販売所で福祉用具専門相談員の経験者
- 福祉用具関連従事者。保健師、看護師、社会福祉士など全10種
- 協会が認めた人
これらに加えて、「福祉用具関連業務の2年以上経験者」であることが必要になります。
以上2つを満たして初めてカリキュラム受講が可能になります。
研修内容
座学48時間、集合研修52.5時間の全100.5時間の研修を完了してカリキュラム修了になります。
「座学の時間が長くて取得が大変そう…」と思うかもしれませんが、e-ラーニング制度が導入されています。
全国で受講可能で、受講料は合計で50000円となっています。
e-ラーニング制度とはテクノエイド協会が設置した福祉用具プランナー研修e-ラーニングサーバーにアクセスし、期間内であれば学習場所・学習時間を指定されず自由に学習できる制度です。
仕事をしながら資格取得を目指す人にとても便利でオススメです。
集合研修は実技研修になりますので場所が指定されます。
修了試験の難易度は?
修了試験は50点満点、30点以上で合格となり福祉用具プランナー研修修了証書書を交付され、資格取得完了になります。
合格率はとても高くなっていますので、しっかり勉強していれば大丈夫です!
他の教育機関において福祉用具プランナー研修修了試験は受験できます。その場合、合格後2年間の福祉関連業務の従事後、修了証明書が交付されます。しかし福祉関連業務の従事2年しないと終了証をもらえません。
そのため、テクノエイド協会での受講をオススメします。
福祉用具専門相談員との違い
福祉用具プランナーと福祉用具専門相談員は名前が似ており混同されることが多いのですが別の資格です。そこで両者の違いを確認しておきましょう。
対象
福祉用具プランナーは先程も述べましたように2年以上の実務業務が必要であるなど細かい条件が多いです。
一方で福祉用具専門相談員は経験の有無の関係なく、学生でも取得可能です。
研修期間
福祉用具プランナーは約100時間の研修、福祉用具専門相談員は約40時間が必要になります。
試験
福祉用具専門相談員には福祉用具プランナーと違って「修了試験は存在しません。」
以上より福祉用具専門相談員の資格取得後、更なる福祉用具の知識を深めるために福祉用具プランナーを取得する人が多いです。
福祉用具専門プランナーを取る人の傾向
どのような人が福祉用具プランナーの資格を希望するかというと、福祉用具の使用方法などのスキルアップが目的の人がほとんどです。
職場での資格条件に含まれることもほとんどありません。ボランティア感覚であったり、介護を突き詰めたいと強い意志を持っている人が多いです。
「福祉用具専門プランナー」は確実に勉強になる資格です。自分の仕事の質を高めていきたいという意志がある人にとっては取る価値のある資格になります。
まとめ
今回は福祉用具プランナーについてまとめてみました。
福祉用具プランナーは福祉用具の専門家である資格で、2年以上の福祉関連の実務と研修を受講することで取得できます。
平成9年の開始当時は100人ほどでしたが今では14000人以上が取得している人気の資格となっています。介護・福祉業界に興味がある方はぜひチャレンジしてみてください。