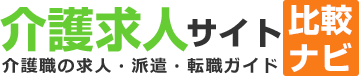社会福祉主事任用ってどんな資格?メリットから資格取得方法までを徹底解説! 作成日:2018.10.01
最終更新日:2020.01.17
あまり聞き慣れていないという方も多いであろう「社会福祉主事任用」ですが、実は介護の職にとっても身近な資格なのです。
今回はそんな社会福祉主事任用について、資格の概要や資格取得のメリット、資格取得方法まで詳しく解説していきます。
そもそも社会福祉主事ってなに??
各都道府県や市町村に設置されている公立の福祉施設や事務所などに勤務し、福祉の業務に関わる公務員のことを社会福祉主事といいます。
社会福祉の法によって定められている援護・更生に関する事務を行うために、福祉事務所では社会福祉主事を設置する義務が設けられています。
社会福祉主事資格は社会福祉法第18条・19条において資格の定義付けがなされている任用資格です。
任用資格って何?
任用資格とは、社会福祉主事になる資格があるということを表すものです。
ですから、実際に公務員の社会福祉主事になるには、この社会福祉主事任用の資格を取得したうえで公務員試験を受けて公務員にならなければいけません。
ただ資格をとればすぐに社会福祉主事の公務員として働けるわけではないということです。
単純な資格としての使い道もある!
公務員の社会福祉主事では任用資格としての要素しかない一方、社会福祉施設職員等として働くには正当な資格として活用できます。
またその他様々な職種の募集において社会福祉主事任用の資格が役に立つことがあります。
よって社会福祉主事任用は福祉に関する職種の基礎的資格として準用されています。
「社会福祉主事」はいつできた?
社会福祉主事任用資格は1950年(昭和25年)5月に制定されました。
社会福祉の資格の中では最も古いものとして知られています。
戦後の1946年(昭和21年)に日本国憲法を制定したとき、国民が「健康で文化的な生活を営む権利」として生存権を保障し、社会福祉がととのえられるようになりました。
社会福祉主事の仕事は?ソーシャルワーカーとしての働き
社会福祉主事は、高齢の方・障害がある方やその家族が日常生活を送るための支援を行うソーシャルワーカー(ケースワーカー)として働きます。
基本的には社会福祉事務所で生活保護の相談などを行いますが、その他にも老人介護の福祉施設や身体障害者・知的障害者の福祉施設、児童福祉施設や母子福祉施設などで業務にあたることもあります。
また、社会福祉施設の施設長や社会福祉協議会の福祉活動専門員として働くこともあります。
社会福祉主事は非常に幅広い場で活躍できる仕事なのです。
社会福祉主事の一日
それでは、実際のソーシャルワーカーとしての一日を 見てみましょう。
- 8:15 職場に出勤
- 8:30 朝礼 当日の予定を確認したり、情報を共有したりします。
- 9:00 面談 午前中は内勤で、来訪者との面談を行います。そのほか、電話での問い合わせ対応なども任されます。
- 12:00 休憩
- 13:00 生活保護申請者の訪問調査
- 17:00 事務所へ戻る
- 19:00 退勤
職場の人に挨拶を済ませ、落ち着いて仕事の準備を整えます。
それぞれの自宅に行き、現在の生活状況などについて調査を行います。1日に数件回ることもあります。
先ほど行った訪問調査報告書をまとめたり、 メールチェックなどをします。
時には残業があったりもしますが、基本的には定時退社 できます。
社会福祉主事任用資格を持つメリットはたくさん!
活躍できる場がたくさんある!
上記でも述べたように、社会福祉主事任用は福祉の仕事の基礎的資格となっているため、この資格を持っていれば様々な福祉の現場で活躍できます。
実際に介護や福祉の求人を見てみると、社会福祉主事任用資格の所有を条件としている求人や、資格を所有していると有利となるような求人がたくさんあります。
そのような求人の職種としては、有料老人ホームや特別養護老人ホームの生活相談員、デイサービス、病院の医療相談員があります。
幅広い分野で活躍できるのが特徴です!
福祉事務所の公務員として働くことができる!
福祉事務所や相談所に公務員として勤務したい、という場合に社会福祉主事任用は必須になります。
他の資格を持っていても福祉事務所の公務員としては働けないので、この資格を持っていれば活躍の場がさらに広がることになります。
公務員として福祉の仕事につけることはかなりのメリットになるのではないでしょうか。
社会福祉士の資格よりも簡単に資格取得が可能!
社会福祉主事任用とよく似た資格として社会福祉士があります。
業務としての違いはそこまでありません。
違いとしては、社会福祉主事任用が「任用資格」であることに対し、社会福祉士は「国家資格」となっている点です。
国家資格である社会福祉士は試験の内容が難しく、合格率も25%ほどと低くなっています。
出題範囲も広いため、独学で資格を取得するには難しく、働きながら資格を取得することも困難です。
それに対し社会福祉主事任用資格の取得の難易度は低く、短期間で資格の取得が可能です。
社会福祉士と似たような仕事でありながら簡単に資格を取得できるのは大きなメリットといえるでしょう。
社会福祉主事任用資格の取得方法!
資格の取り方と必要な科目は?
社会福祉主事任用資格を得るためには以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
1.大学、短期大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者
2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の過程を修了した者
3.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
4.上記の1~3に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者として厚生労働省令で定める者
指定科目に関しては大学の卒業年によって異なっているので、厚生労働省のホームページでしっかり確認しましょう。
任用資格の証明はどうやってするの?
試験を頑張って合格しても、社会福祉主事任用資格には、いわゆる「資格証明書」といったものは存在しません。
そのため、履修済みの科目が記載された成績証明書および大学等の卒業書を就職先に提出することになります。
また、一部の大学では指定した科目だけを抽出した履修証明書を発行してくれるところもあるので、一度学務に行って確認してみるといいですね。
社会福祉主事の給料
公務員として働く場合
社会福祉主事は、地方自治体の「一般職」または「福祉職」として採用されます。
給料は公務員給与規定に沿った額となります。
総務省の出している情報によると、一般行政職の平均年収は約441万円、福祉職の平均年収は約445万円となっています。
たとえば、平成27年度における東京都の場合、行政職として採用された人の初任給は217,440円(地域手当も含めて)となっています。
また、ボーナスを加えた25歳係員の年収モデルは3,552,000円となっています。
しかし、各自治体によっては社会福祉主事を行政職ではなく福祉職で採用することも。
この場合、行政職よりも若干給与が低めに設定されている場合もあるのでご注意を。
詳しくはそれぞれの自治体の給料表で確認してみてくださいね!
民間企業で働く場合
もちろん、経験や勤続年数に応じて給料は上がりますが、全体の平均年収は300〜500万円程度といわれています。
飛び抜けて高額な収入は期待しにくいかもしれません。
しかし、「介護福祉士」や「ケアマネジャー」などの資格をとり、仕事の幅を広げたり、経験を積んだりして管理職に昇進したりした場合は、どんどん収入アップも目指せます。
社会福祉主事任用資格を取得して仕事の幅を広げよう!
以上、社会福祉主事任用について解説してきました。
社会福祉主事任用資格は他の福祉・介護の資格より比較的簡単に取得できるうえに、持っているだけで仕事の幅がぐんと広がります。
現在働いている方でも仕事をしながら資格を取得することが可能です。
無資格で福祉や介護の仕事についていることに不安を感じる方にとって、入門資格としてうってつけの資格です。
転職する際の仕事探しにも便利なので、ぜひ取得してみてください!