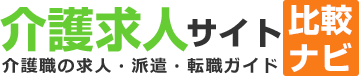生活相談員になるために必要となる資格要件 作成日:2017.10.23
最終更新日:2019.10.30
生活相談員とはどのようなことをやっているのでしょうか。
また、どのような人やどのような資格を持っている方が従事できるのでしょうか。
今回は、生活相談員に求められている資格要件について分かりやすくまとめてみましょう。
今回は、生活相談員として働くために必要なもの、さらに、地域によって異なる資格要件というテーマの2つに分けてまとめていこうと思います。
生活相談員とはあまりメジャーな職業ではありませんが、深くまで知ることで身近な存在として感じられる様になりたいですね。
生活相談員ってどんな仕事?必要なものとは
生活相談員とは資格名称ではなく、職種名称です。
生活相談員には、社会福祉主事に準ずる資格要件が求められます。
そして、生活相談員は資格名称ではないので資格証というものはありません。
代わりに資格要件を満たす社会福祉士などの各資格の証明書等で証することとなっています。
社会福祉士の他には、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格でも良いです。
また、各都道府県でことなるところもありますが、介護支援専門員、介護福祉士、特別養護老人ホームなどで介護提供に関わる計画作成で1年以上実務経験があるもの、老人福祉施設の施設長経験者などがあります。
そもそも資格要件とは?生活相談員の場合
資格要件とはなんぞやって思いませんか。
資格って付いているけど、資格じゃないなんて、と感じますよね。なぞなぞみたいで何だか難しいです。
まず、この意味について理解を深めていきましょう。
資格とは、社会的な意味として、専門能力を証明するといった意味合い、民法上の法人の社員の身分という意味合い、応募資格や採用資格といった意味合いの3つに分けられます。
今回の資格要件では、1つ目の意味合いと3つ目の意味合いを持ち合わせていると考えられます。
そして、要件とは重要な条件のことを指します。
生活相談員に資格じゃなく、資格要件を求めていることは、様々な分野の人に生活相談員になる資格があるとさせることで、この職業で働く人たちに多様性を持たせようとしているのではないかと思われます。
同じマニュアルを勉強している人たちしかいないのはなんだか相談しづらいですよね。
多様性を持たせて、さまざまな種類の質問に対応をできるようにしておこう、というわけです。
生活相談員の資格要件
生活相談員という職種は、法令、省令、通知などによって資格要件が定められています。
社会福祉法第19条第1項各号においていずれかに該当、またはこれらと同等以上の能力を有すると認められることが条件とされています。
また、そこには、社会福祉主事は、都道府県知事または市町村の補助機関である職員とし、年齡20年以上の者であり、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉増進に熱意があり、かつ次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならないとあります。
1 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校または、旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者。
2 厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を終了した者。
3 社会福祉士。
4 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者。
5 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者。
同等以上の能力を有する者として認められるのは、社会福祉法施行規則に定められています。
そこに書かれているのは、社会福祉士、精神保健福祉士、学校教育法に基づく大学において、法第19条第1項第4号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第67条第2項の規定により大学院への入学を認められた者となっています。
地域で異なる資格要件ってどんなものがあるだろう
神奈川県川崎市では、2年以上の介護経験がある方を対象にして、生活相談員としての資格要件を満たしています。
さらに、愛知県では保育士の資格を持つ人も同様に認められています
保育士の資格を持つ人がいるなんて、小さなお子様がいる家庭は相談しやすく、すごく心強いですよね。
こういったように自治体ごとに資格要件を柔軟に変えることは、地域の特色に対応できる工夫と言えるのではないでしょうか。
やはり、地域ごとに問題となることは違いますよね。
しかし、こういった工夫が地域の人たちの信頼を得るきっかけとなっているはずですよね。
生活相談員として
生活相談員には資格というものはありませんが、だからこそ親身になって相談を受けることができる人が多く働いている気がします。
生活相談員について少しは理解頂けたでしょうか。
今後さらに、身近な存在となり、頼れる地域パートーナーとなることでしょう。
ぜひ、みなさんも何か困ることがありましたら相談してみてください。
きっと、親身になって相談にのってくれることでしょう。
今後、この職業の社会的重要性が増して、活躍される立場になることが楽しみですね。